<当ページにはプロモーションが含まれています>
- 米国ETFの積立投資を検討中
- 米国ETFでドルコスト平均法を使おうとして挫折した
- どうにか米国ETFを買いたい
米国ETFの積立投資をしている方って多いですよね。
投資家としても有名な厚切りジェイソンさんも米国ETFの代表銘柄であるVTIを購入されています。
なめくじもつみたてNISAの次の投資ステップとして米国ETFの積立購入を設定しました。
設定しましたがその時に気づいてしまったのです。
「米国ETFが高くてドルコスト平均法が使えない」という問題に…。
きっと自分が当たる壁なら多くの人が当たるに違いないと思い、その解決方法についてまとめてみました。
優良な米国ETFへの投資を諦めるのはとても勿体ないので、ぜひ記事を参考にしてください。
米国ETFの積立購入特有の問題点とその解決方法
- 頑張って入金力を高める
- VTIやSPYDなどの価格が安いEFTを選ぶ
- お目当てのETFに乗っかった商品を選ぶ
- ドルコスト平均法を諦める
米国ETFとは
米国ETFとは読んで字のごとく、アメリカ発のETFのことです。

最近は米国ETFを買える証券会社が多くなって大助かりですね
本ブログでもよく取り上げていますが、アメリカの金融市場はとても力強いため米国ETFへの投資は王道中の王道と言えます。

アメリカ人ならS&P500連動ETFを買い続ければ勝ちみたいなとこあるな
有名なETFには「VOO」、「VTI」、「IVV」、「SPYD」などがあります。
これら有名どころにはインデックスやアクティブ運用のETFが多いですが、一部にはスマートベータ運用と呼ばれる特殊なETFもあります。
米国ETFでのドルコスト平均法の問題点とは?
さて本題に入っていきましょう。
米国ETFでドルコスト平均法を使おうとすると「ある問題」にぶつかります。
それは「米国ETFが高くてまともにドルコスト平均法を使えない」という問題です。
例えばS&P500連動型ETFであるVOOは2022年3月時点で400USD(=米ドル、日本円で約48,000円)以上です。

お高く止まりやがって…
そして米国ETFは日本の単元未満株や投資信託のような少額投資はできません。
「つみたてNISAを満額投資してもちょっと余るから米国ETFでも買おーかなーウフフ」なんてウキウキで探しても、大部分の米国ETFは買えません。
なんとか資金を捻り出して買ったとしても、入金力が低すぎてドルコスト平均法の大きなメリットである自動調整能力が全く働きません。
先に出たVOOの例で考えてみましょう。
月100万円の積立金額なら400USD時点で22口、350USDなら26口、450USDなら20口といったように購入数を自動調整してくれます。

これなら十分ドルコスト平均法が生きていると言えます
しかし月6万円の積立金額では350USDだろうが450USDだろうが1口購入しかできないため自動調整も何もありません。
つまり月6万円の入金力ではVOOのドルコスト平均法は不可能ということです。
米国ETFでのドルコスト平均法を可能にするために
さて、ここからが解決編になります。
米国ETFでドルコスト平均法を可能にするためにはどのような方法があるでしょうか?
これからなめくじが提示する以外の方法もあるかもしれませんので、知っている方はぜひTwitterで教えてください!
では1つずつ見ていきましょう。
頑張って入金力を高める
入金力が足りないなら高めてしまえばいいという脳筋解決法です。

力こそパワー
残念ながらこれは万人にお勧めできる即効性の高い方法ではありません。
しかし、たくさんお金を稼いだり節約すること自体は絶対無駄になりません。
今後の資産形成を有利に進めるために入金力を高める意識は常に持っておきたいところです。
VTIやSPYDなどの価格が安いETFを選ぶ
例えば「VTI」は2022年3月現在で227USD、「SPYD」は同43USD、「VYM」は同112USDです。
これらの単価が安い米国ETFを選択するのは一つの手段です。

VOO見てからだとめっちゃ安く感じる
ただし、米国ETFだから/安いからといって優良ETFとは限りません。
それぞれがどういうコンセプトのETFなのか、それに配当利回りや経費率などをしっかりチェックした上で選びましょう。

安かろう悪かろうのETFにブッ込んだら、後で泣きを見ますよ
お目当てのETFに乗っかった投資信託を選ぶ
ややこしい話ですが、世の中にはETFに乗っかった投資信託というものがあります。
例えば「楽天・全米株式インデックス・ファンド」はVTIに投資する投資信託です。
遠回りではありますが、これならば100円からでもVTIを買うことができます。
同様に先のVOOには「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」経由で投資できます。
これら投資信託を選ぶというのも選択肢の1つです。
欠点は中間ファンドが存在するため、その分の手数料が上乗せされることです。
しかし有名ETFを100円から買えるのは、欠点を補って余りあるほどのメリットです。
ドルコスト平均法を諦めるver.1
発想を変えてドルコスト平均法を諦めるという選択肢もあります。

なるほど確かにね…ってアホか!

いやいや、ほんとにこれも現実的なんですよ
邪道ではありますが、多少のリスクを飲み込みつつ手動で積み立てていきます。
例えば以下のようなやり方です。
- VTIを1口だけ定期購入しておき、余剰資金が出た時だけ買い増しする
- 価格が下がった時だけ、余った資金で買い増しする
これらは一般的なETF購入法とドルコスト平均法のハイブリッドと言っていいでしょう。
ドルコスト平均法を諦めるver.2
こちらはver.1と違って、現金パワーを貯めておいて「安くなった時だけ」買い増していく方法です。
過去のアメリカ市場のチャートを見ると、暴落を繰り返しながらも長期で右肩上がりを続けています。
米国株式市場の成長を信じるなら多少購入タイミングをミスっても理論上は勝てるはずです。

知らんけど(関西人)
最後に
いかがだったでしょうか。
つみたてNISAやiDeCoを枠上限まで投資した人の多くは、次の一手として米国ETFの積立購入を考えると思います。
しかし投資信託と同じような感覚で始めようして本記事の問題点にぶつかるのではないでしょうか。
そこで投資を諦めては資産形成の道が閉ざされてしまいます。
記事内の解決方法が全てではありませんが、少しでもあなたの投資の道が続く参考になれたら幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23a1bbfb.3e992ae6.23a1bbfc.c549d876/?me_id=1278256&item_id=20596353&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8140%2F2000010558140.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

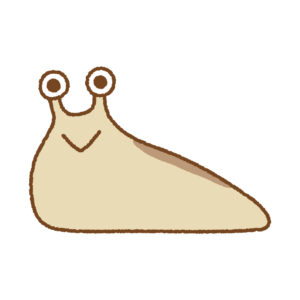


コメント