個人投資家にとって永遠のテーマである「ドルコスト平均法vs一括投資」。

賃貸vs持ち家論争みたいなもんやな
これから投資を始める人も、投資を始めたての人もどちらにすべきか気になるところだと思います。
手垢にまみれた話題ですが、本記事では今一度そのメリットデメリットを取り上げて整理しておきます。

先に言っておくと、基本的に一括投資が優れていると思っています
最終的にはその人の状況によって選択肢が変わってきますが、その条件を知っていただければと思います。
ぜひ正しい知識を得て、投資ライフに生かしていきましょう。
結論
- ドルコスト平均法は攻守のバランスが良い投資法
- 一括投資は攻撃特化型の投資法
- 最大リターンを狙うなら一括投資だが、合うかは人次第
ドルコスト平均法と一括投資とは
まずは知識のおさらいからです。
ドルコスト平均法
ドルコスト平均法とは、まとまった資金余力を”敢えて”1ヶ月毎など定期的に積立投資をする方法のことです。

資金余力が無い場合は単に逐次一括投資してるだけや

金融機関の説明ですら間違ってるんですよね…担当者サン…
例えば手元に100万円の資金余力があったとして、それを1ヶ月5万円ずつ20ヶ月かけて投資するというのがドルコスト平均法となります。
なおドルコスト平均法はある程度の中長期スパンでの投資法となるため、「最終的に投資対象は値上がりしていくのを前提としている」ことに注意してください。
一括投資
一括投資は読んで字の如くで、資金余力を全て1回で投入する投資方法です。
1回資金余力が空になって、資金ができ次第また全て投入するのも、広い意味では一括投資となります。

「月1万円ならギリ投資できる」場合は、どちらかと言えば一括投資です
ドルコスト平均法のメリットデメリット
さて本題のメリットデメリットを解説します。
まずはドルコスト平均法からです。
ドルコスト平均法のメリット
ドルコスト平均法のメリットは以下の通りです。
- 下げ相場で平均取得単価を下げられる
- レンジ相場でも大きく失敗することが無い
- 投資タイミングを監視する手間が無い
- 相場の変動に心が惑わされない
- いつでも一括投資に切り替えられる
- フリーキャッシュが手元に残る
簡単に総評すると、「攻守のバランスが良い投資法」と言えます。
ドルコスト平均法をゲームで例えるなら、片手剣と盾を装備した戦士タイプの扱いやすい投資法です。

広く推奨される訳やな
①〜⑥について順に細かく説明していきます。
下げ相場で平均取得単価を下げられる
もっとも大きく、また声高に叫ばれるメリットがこの取得単価を下げる効果です。

カッコよく言うと「取得単価の平準化」です
株や投資信託などは、基本的に日々上がったり下がったりなどの細かな値動きを繰り返しています。
またそのうねりは日毎以外にも、週毎、月毎、場合よっては年毎の場合もあります。
もし細かなうねりを起こしながら相場全体が下げ基調にある(=下げ相場である)場合は、一括投資をしたらその後に含み損を抱えることになります。
しかし下げ相場においてドルコスト平均法で投資した場合は、次回購入時は更に価格は下がっており、そのまた次回はもっと価格が下がっています。
こうして全ての資金余力を投入し終わった時点で取得単価を均すと、一括投資よりも必ず低くなります。
現実にはそんな常に下がり続ける相場は早々ありませんが、下げ相場という条件さえ満たせば多少の誤差があろうとドルコスト平均法が有利です。

後述するが、この性質はデメリットと表裏一体や
レンジ相場でも大きく失敗することが無い
先ほどは下げ相場の話ですが、今度は細かな変動を起こしながら価格が大きく変化しないレンジ相場の場合を考えてみましょう。
投資するタイミング(例えば毎月○日に投資と設定する)によっては若干の高値掴みが起きることもありますが、同じくらい安値掴みする可能性もあります。
結果的にはレンジ相場であっても取得単価の平準化が多少起きるので、ドルコスト平均法で大きく失敗することはありません。

ま、一括投資でもレンジ相場で事故ることは少ないですけどね
投資タイミングを監視する手間が無い
取得単価の平準化とともにドルコスト平均法の大きなメリットの一つが、手間のかからなさです。
一括投資を含む通常の投資法で大きな利益を上げる場合は、安値を掴む(場合によっては高値で売却する)必要があります。
言葉では簡単ですが、現実に安値を見極めて投資するのは容易ではありません。

そんなこと簡単にできたら投資家はみんな金持ちや
例えば株価は最新ニュースを常に摂取し、経済と投資の知識をつけ業界や企業の分析をして、やっと高い安いがうっすら見えてくる程度です。
それを基に、常に変動する値動きの中でタイミングよく投資するというのは非常に手間がかかり不透明です。
その点、ドルコスト平均法は「分からんもんは分からん」と割り切った投資手法であり時間で分散を図っています。
結局のところ、タイミングを見極めずに淡々と資金を投入するため、初期設定さえしてしまえば後は手間要らずということです。
相場の変動に心が惑わされない
手間がかからないメリットと似ていますが、タイミングを見極めないということは相場の変動に心が惑わされないのと同義です。
一括投資をした場合は、その後に値下がりしないかとても気を揉みます。

要は高値掴みしなかったか心配になるということです
場合によっては早期に売却=損切りを考えることになるかもしれません。
そうなると折角長期では値上がりが見込めるのに、目先の含み損でマーケットから退場していく、こういったリスクを含んでいると言えます。
その点ドルコスト平均法は「相場は読めない、けれど中長期では値上がりしていく」という前提で投資する手法ですので、相場の変動を見る必要がありません。
一度設定すれば後は勝手に自動投資されるため、投資していることすら忘れかねない。
こういった精神力を消耗しない投資手法であることは、ドルコスト平均法の大きなメリットと言えます。

よく初心者に勧められるのは、このメリットがかなりデカいからや
いつでも一括投資に切り替えられる
意外と各種解説で言及されにくいのが、一括投資へ移行できるというメリットです。
資金余力を残しつつ分割投資するので、状況が変わり一括投資が有利と判断した時に移行することが可能です。
逆に一括投資からはドルコスト平均法には移行できません。

高値掴みしても基本的には耐え忍ぶしかありません
フリーキャッシュが手元に残る
資金余力があるということは、手元に自由にできるキャッシュがあるということです。
もし日常生活でトラブルが発生し、想定外の資金が入用になった場合には投資資金の一部を回すことができます。
一括投資であっても同じことは可能ですが一旦投資対象を売却する必要があり、その時には売却損が出たり売却益に対して課税される可能性があります。

まあそもそも十分な安全マージン取っとけよという話ではある
ドルコスト平均法のデメリット
今度は逆にドルコスト平均法のデメリットについてまとめていきます。
先にドルコスト平均法は攻守のバランスが良い投資法と言いましたが、悪く言えば中途半端・どっちつかずの投資法とも表現できます。
以下がデメリット一覧です。
- 右肩上がりの相場に弱い
- 短期売買が苦手
- 概して一括投資よりリターンが小さい
- 配当金が少なくなる
- 手数料が増える可能性がある
- やることがなくモチベーションを保ちにくい
守備にも意識を持っている以上、どうしても一括投資と比べるとリターン(利益)は小さくなる傾向にあります。

世の中に万能はありません
右肩上がりの相場に弱い
ドルコスト平均法最大のデメリットが右肩上がりの相場に弱いことです。
2021年の米国市場は右肩上がりの、まさにドルコスト平均法が苦手とする相場でした。
例えばみんな大好きeMAXIS Slim米国株式(S&P500)で試算すると、2021/1/4時点の基準価額¥13,339に対し、2021/12/27時点では¥18,836となっています。
この投資信託に100万円を投資していた場合、一括投資では約41万円の利益が出たのに対して月々のドルコスト平均法では約21万円と、リターンが半分近くまで減ります。

手数料は細かいから無視しているぞ
2021年の米国相場はかなり異常であり通常はこれほどの差は出にくいですが、少なくとも右肩上がりの相場でドルコスト平均法のリターンが小さくなることは事実です。
概して一括投資よりリターンが小さい
一括投資と比べるとドルコスト平均法はやや守備寄りの投資法ですので、基本的にはリターンは小さくなる傾向にあります。
後述しますが、種々の条件が揃った時のみドルコスト平均法が一括投資のリターンを上回ります。
しかし強い戦略性を持って投資する場合でなければ、「ドルコスト平均法はリターンが小さくなる」として覚えておくといいでしょう。

重ねて言いますが、世の中には万能はありません
短期売買が苦手
ドルコスト平均法による投資は一般的には年単位〜長ければ20年、30年といったスパンで実施します。
その為、短期売買によって利益を上げていく投資スタイルには不向きです。
具体的にはスキャルピングトレード、デイトレード、スイングトレードに使える投資法ではありません。
もしドルコスト平均法を用いたいなら、時間分散という性質をきっちり表現するために、せめて1年以上をかけて投資すべきでしょう。

1年未満でなんとなく分割するのは、個人的にはナンセンスと思ってます
配当金が少なくなる
投資対象にもよりますが、配当金が出る類のETFや投資信託ではドルコスト平均法による配当金受取額は低くなります。
当然ながら配当金は”すでに投入している資金”に対して発生しますので、逆に言えば手元にあるキャッシュへは配当金が出ません。
もし配当金を使わずに再投資する方向であれば、配当金の複利効果の大部分を捨てていることになります。

配当金を遊びや生活費に使うってんなら複利云々は無視でOK
手数料が増える可能性がある
一括投資と比べるとドルコスト平均法では買付回数が格段に増えます。
もし投資対象が毎回買付手数料が発生するタイプであれば、手数料分(+手数料の複利分)のリターンが削れます。
しかし最近人気の、ドルコスト平均法に適した投資信託やETFは手数料ゼロのものも多くなっていますので、そういった商品であれば気にする必要はありません。

手数料ゼロのことを「ノーロード」と言います
やることがなくモチベーションを保ちにくい
地味に効いてくるデメリットが、このやること無さ過ぎ問題です。
ドルコスト平均法では自動投資設定さえ完了させたら、後は投資資金が無くなるまで放置するだけです。
人は何事も嬉しさやハラハラ感でモチベーションが保てる生き物です。
ドルコスト平均法は手間のかからなさに加えて、目に見えたリターンが出てくるのにかなり時間がかかりますので、非常にモチベーションが保ちにくい投資法と言えます。

やること無さ過ぎて余計な投資に手を出しがち

んで、痛い目みてドルコスト平均法に戻ってくるんですよね
一括投資のメリットデメリット
次に一括投資のメリットデメリットを見ていきましょう。
一括投資のメリット
一括投資のメリットは以下の通りです。
- 上げ相場でリターンを最大化させることができる
- 稲妻が輝く瞬間に立ち会える
- レンジ相場でも大きく失敗することが無い
- 配当金にフルで複利効果が発生する
- 短期売買でも使える
簡単に総評すると、「攻撃特化型の投資法」と言えます。
ドルコスト平均法を片手剣と盾を装備した戦士タイプとすれば、一括投資は大剣を持って切りかかるバーサーカータイプです。

攻撃は最大の防御である
①〜⑥について順に細かく説明していきます。
上げ相場でリターンを最大化させることができる
なんといっても一括投資の最大のメリットは、上げ相場でリターンを最大化させることが可能という点です。
ドルコスト平均法よりもリスクを上げている分、リターンとして跳ね返って来た時は一括投資をして良かったと心から思えるでしょう。

ンギモッヂィイイ
投資というのは基本的に資産を増やしていくゲームですので、リターンを最大化できる一括投資は目的に適った投資手法と言えます。
稲妻が輝く瞬間に立ち会える
インデックス投資の名著「敗者のゲーム」では、長期投資では最も株価が上昇する日(=稲妻が輝く瞬間)に市場に居合わせる重要性を説いています。

この稲妻が輝く瞬間ってのは長期投資家の中ではめっちゃ有名な言葉や
例えば敗者のゲームによれば、過去109年間の市場データでは、ベスト10日を逃すだけでトータルリターンの2/3を失うとされています。
ドルコスト平均法も長期投資の一種ですので稲妻が輝く瞬間に立ち会えはするものの、その時にすべての資金余力を市場に曝せてはいません。
対して一括投資ではその恩恵を100%を受けることができます。
この事実もまた、リターンを最大化させる要因の一つとなります。
レンジ相場でも大きく失敗することが無い
レンジ相場ではドルコスト平均法で大きな損失は出ないことは先述しましたが、一括投資もまた同様に大きく含み損を出すことはありません。

ドルコスト平均法よりは振れ幅が大きくなりますけどね
一括投資が苦しくなるのは、あくまで下げ相場の時だけです。
配当金にフルで複利効果が発生する
投資対象が配当金が出る商品であれば、明らかに一括投資に分があります。
もし配当金を再投資する場合は、その配当金にも複利効果が発生するため、ドルコスト平均法と比べて侮れないリターンの差が生まれます。

配当金がマイナスってことは無いから、ここに関しては一括投資が完勝や
短期売買でも使える
一括投資は長期投資だけではなく、短期売買でも使用可能な投資法です。
短期売買では細かな利鞘(=キャピタルゲイン)を狙いに行きますので、元手が大きければ大きいほどリターンも大きくなります。
その点、今使える資金を全て使う一括投資では短期売買であってもそれなりのリターンが期待できます。

投資に慣れてる人ならレバレッジかけますが、それも一長一短です
一括投資のデメリット
今度は一括投資のデメリットについてまとめてみましょう。
一括投資のデメリットは以下の通りです。
- 投資タイミングの決定に知識と手間が要る
- 下げ相場に弱い
- 資産の変動が激しくなる
- 手元のキャッシュに余裕が無くなる
- ドルコスト平均法に切り替えにくい
- 金融機関によっては手数料が多めに発生する
投資タイミングの決定に知識と手間が要る
一括投資をする場合は、適切な投資タイミングを見極めることが必要です。
なぜなら一括投資はドルコスト平均法と比べてリスクが高い投資法なので、なるべくリスクを下げるために無造作に投資してはいけないからです。
ドルコスト平均法は時間を分散する投資法ですので、投資を始めるタイミングは特に気にしなくても構いません。
しかし一括投資の場合は、例えば明らかな下げ相場で投資してしまうとその後に発生する含み損を回復させるために時間がかかってしまいます。

それでも一括投資を推奨する人は多いけどな
最大投資リターンを得たいと考える場合は、マクロ経済や投資対象、あるいは投資そのものの知識を持ち、かつタイミングを見極めるために監視の手間をかけなければいけません。
下げ相場に弱い
一括投資の最も問題となるデメリットが下げ相場に弱いことです。
得意な上げ相場は元より、レンジ相場であっても大きくリターンの変動はありませんが、下げ相場だけは別です。
例えば大きな世界的金融危機が起きつつある段階で一括投資をすると、その後に激しく資産価値を消耗する危険性があります。

投資対象によっては紙クズ化することも…
資産価値の大きな消耗は、投資家として心理的・経済的に耐えきれなくなって損切りもしくは退場を招きます。
短期投資ではそれも有りですが、長期投資目的で退場すると何のために投資を始めたのか分からなくなります。
資産の変動が激しくなる
ドルコスト平均法は徐々に投資額が増大するのに対して、一括投資ではいきなり最大BETから始まります。
そのため、初期から日毎の資産の変動が激しくなり、投資初心者はその変化に心を擦り切らしてしまいます。

100万円投資したら日々1〜5万円くらい変動するぞ
ドルコスト平均法ではゆっくりと日々の変動が激しくなるので慣れますが、一括投資ではその変動に慣れる期間が無いというのもデメリットとなるでしょう。
手元のキャッシュに余裕が無くなる
一括投資をすると手元のキャッシュはほとんど無くなります。
投資をする場合には生活用の余剰資金を別に確保しておくのが原則ですが、それでも私生活の状況によっては余剰資金以上にお金が必要になることもあるでしょう。
その際には投資資金を引き上げることでキャッシュ化することは可能ですが、適切なタイミングの売却でなくなることがほとんどです。
結局のところ、「何とかできるが投資のリターンの悪化を招く」ということになります。

ある意味退場みたいなもんですからね
ドルコスト平均法に切り替えにくい
ドルコスト平均法はであれば、途中から簡単に一括投資へ切り替えられます。
しかし初手で一括投資を選ぶと、その後にドルコスト平均法に切り替えるのは難しくなります。

厳密な意味じゃ「切り替えられない」というのが正しい
ですので、もし一括投資後に誰の目にも明らかな下げ相場が発生した場合にも、基本的にはダメージが最小限になることを祈って見守ることしかできません。
金融機関によっては手数料が多めに発生する
投資額にもよりますが、金融機関によっては一括投資時に手数料が多めに発生する場合があります。
一般的に証券会社は、1日あたりや1月あたりの投資上限額を設定しています。
もしその上限額を超えると別の投資プランとなって、やや割高な手数料が発生することが多いです。
もちろん一括投資によって得られるであろうリターンよりかは断然少ないですが、手数料増額のデメリットがあることも覚えておくといいでしょう。

例えばSBI証券の現物取引手数料は¥55→最大¥1070/約定となります
ドルコスト平均法と一括投資はどちらがいいのか?
さて、ここまで読んでドルコスト平均法と一括投資の特徴を整理できたと思います。
最後のテーマとしては、結局どちらをすべきなのか?というところを取り上げます。
結論からお勧めすると「一括投資」です。

ただし条件があります
その理由やそれぞれの投資法が適している人を見ていきましょう。
Vanguard社は一括投資推奨
インデックス投資の雄、Vanguard社は一貫して一括投資を推奨しています。
なぜならば、長期投資を前提とするならばいかなるタイミングで投資しようが平均的なリターンが一括投資>ドルコスト平均法となるからです。
もちろん中には投資タイミングを測った上で一括投資したり、ドルコスト平均法を採用すれば短期的にリターンが上振れすることはあります。
しかし世界経済は変動を繰り返しながら長期的には常に成長し続けるという仮定を置けば、ドルコスト平均法を採用した多くの投資家は、一括投資組と比べてリターンが低下します。

そのごく一部の投資家になる自信があるならドルコスト平均法でもいいぞ
ドルコスト平均法はあくまで痛みを分割するだけ
一括投資であろうがドルコスト平均法であろうが、下落リスクには曝されています。

ドルコストだと30%下がって、一括投資だと50%下がることはありません
違いがあるとすれば、資産のうち何%をその下落リスクに晒しているかという点です。
しかしそれも資金投入が完了した以降は、ドルコスト平均法だろうが一括投資だろうが変わりはありません。
本来考えべきは、最終的なポートフォリオ(以下、PF)全体でどれだけのリスクを取るのかということです。
例えばキャッシュと株50:50のシンプルなPFを目指すとします。
ドルコスト平均法を採用して分割投資している間は、キャッシュ90:株10→キャッシュ80:株20→…キャッシュ50:株50と構成が変化していきます。
その移行期間はPF全体として株価下落のリスクは少なめとは言え、逆にキャッシュのままで置いておくインフレリスクを多く抱えています。
もしインフレリスク>株価下落リスクであれば、投資資金をキャッシュで置いておく意味はありませんよね。

歴史的には実際そうだからドルコスト平均法のリターンが低下する訳や
ちなみにインフレリスクについて詳しく知りたい場合は、以下の記事を読んでください。
心理的安全性ではドルコスト平均法に軍配
とは言え、投資に不慣れな人がまとまった額を一括投資すると日々の資産変動に心が惑わされます。
仮に今までの貯金1,000万円を投資しようとした時に、日々数十万円が乱高下する状況に初心者が耐えられるでしょうか?
残念ながら、多くの人にとっては受け入れがたい現実です。
短期投資はともかく、長期投資では10年15年というスパンで投資を続けてこそ意味が出てきます。
もし投資直後に暴落が始まって1年のうちに1,000万円が500万円分にまでなってしまった時に、耐えきれなくなって売却したら試合終了です。
そこには1年かけて大切な資産を500万円分失ったという結果が残るだけです。

実際にレバナス組と呼ばれる人たちは現在この状態になっています
こうなっては、ドルコスト平均法と一括投資のリターンの違いなど瑣末なことです。
もし神経質だったり心配性だったりする自覚がある場合は、ドルコスト平均法の方が現実的かもしれません。
下げ相場になりそうならドルコスト平均法で始めるのは有り
2022年冬現在では、アメリカ経済の1年以内の景気後退がかなり高い確率で起きるだろうと言われています。
こういった下げ相場が見えている状況で、ドルコスト平均法から取りあえず始めるのは有りです。

なめくじはまさにこのパターンで待機しているぞ
しかしこれは「自分は相場が読める」という非常に傲慢な考えに基づいた投資法です。
今日まであらゆる投資のプロが金融業界でもがき続けても、投資の必勝法は生み出されていません。
つまり歴戦のプロ投資家ですら相場が読めていないのです。
素人である我々個人投資家が、相場を読みながら投資法を決定するという考え自体間違えであり、期待リターンを落とす行為であることは自覚しておく必要があります。
それぞれが適している人
最後にそれぞれの投資法が向いている人の条件を整理します。
まずはドルコスト平均法が向いている人は以下の通りです。
- 投資初心者
- 神経質、心配性
- 生活防衛資金が多くない
- 日々忙しく投資に時間を割けない
- 資産が減る状況をなるべく避けたい
また一括投資が向いている人は以下の通りです。
- 投資に慣れている
- 楽観的、忘れっぽい
- 投資に関して日々情報収集をできる
- 経済的な余力がある
- 最大リターンを叩き出したい
最後に
いかがだったでしょうか。
重ねて言いますが、ドルコスト平均法vs一括投資では一括投資に分があるとなめくじは考えています。

投資に絶対は無いし、過去の実績通りに未来が進むとも限らんがな
また取り上げたVanguard社以外でも、多くの著名な投資家が一括投資を推奨していることも覚えておいてください。
結局のところドルコスト平均法を採用するメリットのほとんどは心理的な安全性を取ったり痛みを軽減する点です。
投資未経験者はこの精神の消耗や痛みのイメージが湧きにくいと思いますので、初心者であればまずはドルコスト平均法で始めて体験することをお勧めします。
逆にすでに色々自分で情報収集し、投資理論も持ちつつあるような人は一括投資していきましょう。

なめくじも相場が落ち着いたら一括に切り替えるつもりです
タイミングを読んで一括投資をするのか、Vanguard社が推奨する通りに手元のフリーキャッシュを逐次全力投球するかはご自身で判断してもらえればと思います。

では次の記事でお会いしましょう!

またな
- ドルコスト平均法は攻守のバランスが良い投資法
- 一括投資は攻撃特化型の投資法
- 最大リターンを狙うなら一括投資だが、合うかは人次第

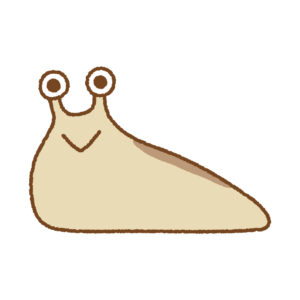



コメント